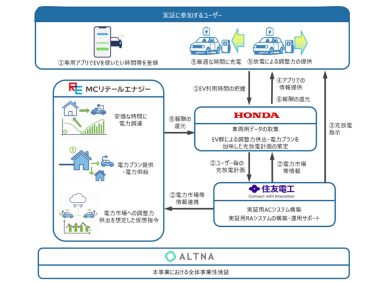2014年10月ドイツのサプライヤーのZFが上海で、ビジネスカンファレンスを開いたというレポートをした。
主な内容はZFがアジアパシフィックエリアを重視したグロバールなビジネス展開をしていくこと、そして未来へ向かうイノベーションとしてのゼロ・エミッションの世界におけるZFがやるべきイノベーションなどについての展望だった。今回は現在のZFが提供している乗用車用ドライブライン・テクノロジーを搭載するリアルなモデルによる試乗会の模様をレポートしよう。
具体的にはパワートレーンを中心としたテクノロジーを完成車両に提供し、販売されているモデルの試乗を上海郊外の天馬サーキットで試乗テストドライブするというものだ。それでは、試乗できたモデルごとにZFのテクノロジーをみてみよう。

BMW3シリーズ。モデルは328iで2.0L+ガソリンターボを搭載し、ZFテクノロジーとして8速ATとトルクコンバーター、前後のシャシーコンポーネンツ、アクスル、電動パワーステアリングが搭載されている。
8速ATは多段化の先頭を切ってマーケットに投入されたトランスミッションで、欧州のダウンサイジングコンセプトと密接にリンクしている。小排気量化されたエンジンは過給器によりトルク、パワーともにロスした排気量以上の出力を得ている。しかし、出力特性は低回転化が進み、低速からでも最大トルクを発揮するように変化している。必然的にエンジンスピードの減速が必要で、高回転まで回さずとも走れるギヤが必要となっているわけだ。
ZF8速ATは対応トルクによって2種類あるが、いずれもFR用のトランスミッションである。シフトフィールは滑らかで全速域ロックアップを持つため、ダイレクト感のあるATとなっている。そのため欧州のプレミアムブランド御用達となっている。BMWの多くにこのトランスミッションは搭載され、他にもジャガー、アウトンマーティン、ベントレー、ロールス・ロイス、レンジローバーなどにも採用されている。
シャシーコンポーネンツはアーム類も含めたアッシーで、ダンパーにはSACHSが採用されている。SACHSの開発の特徴にフラットベルトによるテスターが上げられる。通常ダンパーテスターはダンパー単体を垂直にした状態で連続稼動テストをするのが一般的だが、SACHSではシャシーとセットした状態が再現できる。キングピン軸を設定した上での連続稼動テストができるため、目標とする減衰値が装着状態で設定できる特徴がある。
電動パワーステアリングはステアリングラックにベルトを掛けた第3世代のEPSでEPSapaという電動パワーステアリングを装備する。電動アシストによる違和感はなく、油圧との区別をつけることが難しいほどナチュラルにセッティングされているのが特徴だ。
これらのZFパーツによってジオメトリーはニュートラルで、いち早くアクセルを開けることができる。もちろんESCが装備されているため、少々早めのアクションでも素直にコーナーをクリアする。ハンドリングでは世界のベンチマークとされる3シリーズは、ZFのシャシーテクノロジーによって構築されていることが体験できた。また、スムースで上質な変速をする8速ATはサーキットでも上質でありながらダイレクト感のあるしっかりしたフィールだった。
 レンジローバー・イヴォークには9速AT、シャシーコンポーネンツ、電動パワーステアリングが搭載されている。9速ATはZF最新のFF用トランスミッションで(9速ATの詳細試乗記事はこちら)、やはり対応トルクによって2種類ある。現在はディーゼルエンジンとの組み合わせた完成車はないが、もちろん対応が可能だ。
レンジローバー・イヴォークには9速AT、シャシーコンポーネンツ、電動パワーステアリングが搭載されている。9速ATはZF最新のFF用トランスミッションで(9速ATの詳細試乗記事はこちら)、やはり対応トルクによって2種類ある。現在はディーゼルエンジンとの組み合わせた完成車はないが、もちろん対応が可能だ。
9速ATは1速がエキストラローギヤードに設定されているため、2速発進となる。4WD車への対応のためのギヤだ。さらにギヤ比は5速が1.00となるため、6速以上はオーバードライブとなり、省燃費への貢献度が高い。実際、イヴォークでは120km/h巡航時6速ATより16%以上省燃費となる。変速比幅は9.81と広く、ワイドレシオ・スプレッドのCVTでも現状6.5程度が限界であるから、その広さが分かる。結果、エンジンスピードは6速で2890rpmに対し9速では2170rpmという回転数になり、燃費がいいと実感できるだろう。
サーキットでの試乗ではパドルシフトを使い、その変速スピードを試すが、文句無く素早い変速とそして飛びギヤ変速もするので、イヴォークと言えどもサーキットを攻める走りまで試すことができる。
ポルシェ911タルガ4Sには7速デュアルクラッチのPDKを搭載。もちろんこれもZF製である。さらにシャシーコンポーネンツ、電動パワーステアリングが装備されている。PDKはポルシェのデュアルクラッチの呼称で、7速のツインクラッチである。
ポルシェ911でのサーキット走行は気持ちよく、初めはさまざまなフィールチェックをするが、気づけばアクセルを全開で床まで踏みつけ、コーナーへの侵入までもブレーキを遅らせている自分に気づく。ポルシェのDNAが乗る者に自然と伝わり、だれもが楽しくスポーティに走りたくなるのだと実感した。
PDKの変速は言うまでもなくダイレクトで変速スピードは申し分ない。パドルシフトを使い、軽快に回るエンジンに酔いしれた。RRというレイアウトはハンドリングに特徴があるものの、これぞポルシェという楽しさがある。滑り出しも穏やかでドライバーにしっかり情報が伝わり、そしてEPSの制御も働き飛び出すこともない。もっとも攻め過ぎてタイヤグリップの限界を超えてしまえば電子デバイスの出番はなくなる。
最後に中国製のSUVにも試乗できたのでレポートすると、ZF製品としては6速ATを搭載していた。車名はJMC(江鈴汽車)のSUV、 Yushengという2.4Lディーゼルターボエンジンを搭載していた。インテリアはレザーシートもおごられ中国のプレミアムモデルと想像できる。実は車両に関する資料がなく、またZFも自社製品の情報までしか開示できないため、詳細は不明だ。

日本車では高価なZFのトランスミッションを搭載しているクルマは存在せず、中国のクルマには存在するというのは日本人として複雑な気持ちだ。というのもこの6速ATはZFの第2世代で、人間の知覚できないレベルのレスポンスタイムに到達したトランスミッションで、中国市場向けに上海の工場で生産されている。2014年現在250ユニット/day生産され、2018年までには合計50万ユニットが生産される予定ということだ。
トランスミッションは別としても国内自動車メーカーは「開発の集中と選択」はこの先必須になると想像できる。これまでのように、何が何でも自前主義でボトムアップを目指す時代からはいち早く脱却し、メガサプライヤーとの協業が時代をリードし、トレンドを作っていくと想像できるからだ。
ZFは2015年に日本国内にR&Dを建設するという。ZFAPのCEOルディ・マイスター氏によれば「自社製品のアピールの場としてだけでなく、日本の技術を学ぶ場所である」とは言っているが、この控えめなコメントから逆に自社製品の自信の表れとも受け取れるわけで、ジャパン・ブランド=all made in Japanである必要がないことは明白だ。だからこそ日本車が世界のベンチマークとなる日を待ちたい。
<高橋アキラ/Akira Takahashi>