注目のスタートアップ企業でシリコンバレー発「アプライド・インテュイション」の共同創業者カサール・ユニスCEOが来日し、メディア向け会見を行ない、最新の自動運転技術や高度運転支援システムの現状を説明した。

アプライド・インテュイションは、2017年にカリフォルニア州で創業された自動運転技術、高度運転支援システムの開発、さらに開発ツール、シミュレーションツールの販売を行なう自動車知能化技術のソフトウエア企業だ。
カサール・ユニスCEOはGM、ボッシュ、Googleでキャリアを積み、自動運転技術でのベンチャーとなり、アプライド・インテュイションを設立した。
同社の自動運転技術は乗用車に限らず、輸送トラック、農業トラクター、建設機械、鉱業用大型車両、そして軍用車両までを対象としている。
アプライド・インテュイションは、投資ファンド市場でも高い評価を受けており、2025年には860億円の調達を完了し、自己資本も充実させ、市場では2兆円を超える途方もない評価額が決定しているなど、注目のスタートアップ企業となっている。
このアプライド・インテュイションは、現在では世界の自動車メーカーのトップ20社のうち18社とビジネスを展開している。日本メーカーではトヨタ(TRI、現在はウーブンbyトヨタ)、いすゞ、日産、世界ではフォルクスワーゲン・グループとビジネスを展開し、特にポルシェとは自動運転技術で提携を行なっている。「グローバル・ビークル・インテリジェンス・サプライヤー」と自称しているのも納得である。
アプライド・インテュイション主なビジネスは、車両ソフトウエアの開発・検証ツール、車両OSプラットフォーム、自動運転ソフトウエアの販売となっている。

ユニスCEOは、現在のビークル・インテリジェンスは自動運転、高度運転支援システム、最新の車両OSを使用したインテリジェント・キャビン、インテリジェント機能を迅速に開発するための開発ツールが3本柱になっていると説明した。
特に自動運転、高度運転支援システムは、高品質で豊富なデータに支えられたE2E(エンド to エンド)モデルの実現により大幅な性能向上を果たしている。
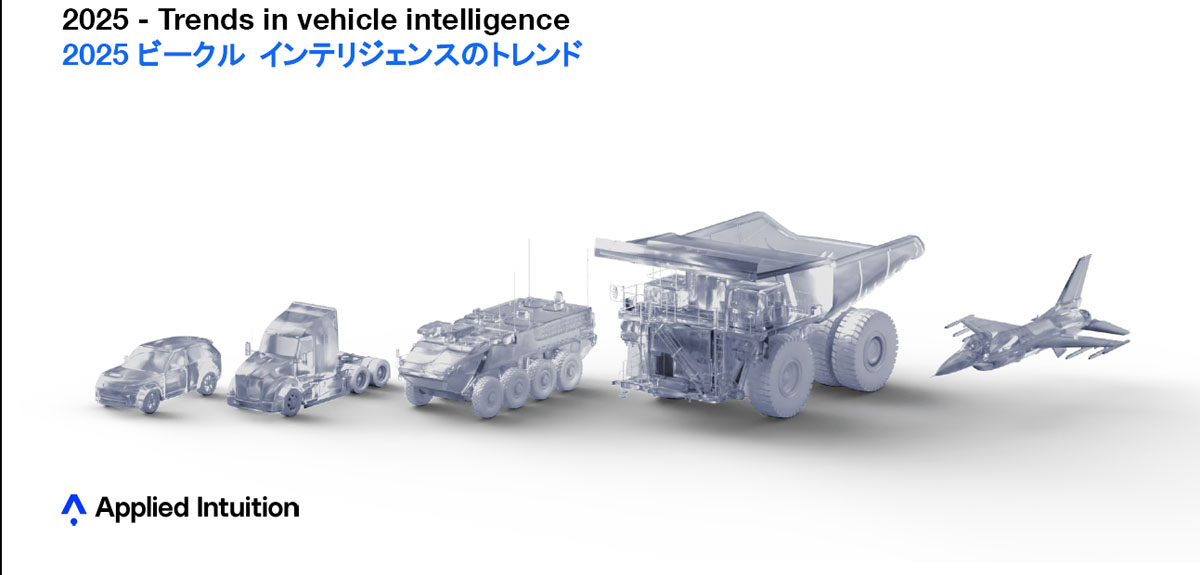
E to Eの自動運転は、大規模な人間の運転データと外部データをベースにして、AIとシステムが運転行動を計画・立案し、人間の運転を模倣する技術がベースになっている。こうした模倣学習に基づく運転は人間の運転性能に限りなく近づくことができる。
こうしたエンド to エンド自動運転をすでに採用しているのが、アメリカの自動運転タクシー「Waymo(ウエイモ)」で、サンフランシスコではシェアライド市場で25%以上のシェアを占めるに至っている。
また中国に眼を転じると、ファーウェイの車両OSがすでに多くの中国メーカーに採用されてソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)化を実現しており、「ファーウェイインサイド」と呼ばれるような状態になっている。
BYDは、「ナビゲーション on オートパイロット(NOA)」と呼べるレベル2.5の高度運転支援システムを大量かつ低価格で市販モデルに展開しており、2025年4月以降に販売されたBYD車の57%に搭載されている。
つまり中国市場ではもはや車両OSを搭載したSDV車両は常識化しており、BYD、ファーウエイ、モメンタ、シャオミなどが激しいシェア競争を繰り広げ、高速道路だけでなく、市街地道路での「ナビゲーション on オートパイロット」も多くの車両に搭載されている。
また、車両OS、ソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)化のコストも大幅に下がっており、この結果、中国以外の自動車メーカーが市場シェアを急激に失っているわけだ。
他国の自動車メーカーはもちろん、アプライド・インテュイション社にとって、これは脅威であるが、政治的、地政学的なハードルにより、今のところは他国への展開が難しいことが中国勢の大きな弱点になっているのだ。

商用大型トラックの分野では、日本だけではなくアメリカでもドライバー不足の深刻化や離職率の高さにより、将来の貨物輸送需要に対応するため、自動運転技術の導入がますます重要となっている。そのため、レベル4の自動運転技術は、乗用車より先に大型トラックの分野で実用化される見通しとなっている。
一方、中国では、すでに大型トラックでレベル2.5の高度運転支援システム、またはレベル3の自動運転が急速に採用されつつあるが、アメリカにおいてはレベル4の自動運転を目指して多くの運輸企業が取り組んでおり、世界的に見てもリーダーになっている。
建設用、鉱業で使用される各種の車両では、自動運転・自動搬送システムと自律型ドローンの導入により業界は大きな変革を迎えている。アプライド・インテュイションは不正路面の地形でも自動運転・自動搬送が可能なシステムを市場投入しており、今後それらの技術は急速に拡大すると予想される。
さらにロシアのウクライナ侵攻でも、インテリジェントかつ手頃な価格の大量生産兵器が戦場の常識を覆して普及しており、今後は軍用車両なども含めてインテリジェント技術の採用拡大は必須となっている。
このような現状から、日本の自動車メーカーは早急に車両OSの採用、ソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)の実現が求められているが、一方で高コストなSDV化は長期的に見れば限界があり、より迅速で、より低コストの開発が求められている。
そのためにはこのアプライド・インテュイションのような技術パートナーの存在が不可欠だとユニスCEOは語っている。
そして、中国の自動車メーカーに打ち勝つことができる競争力のあるソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)の実現にはAIの組み込みが欠かせず、そのためにはすべての自動車メーカーは早急にAIを駆使することができる企業に生まれ変わる必要があるとユニスCEOは語っている。















