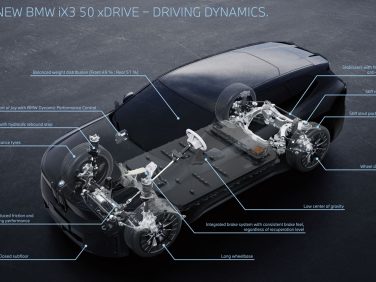マニアック評価vol41
かわいいルックスで人気のフィアット500に、新たに革新的なツインエアエンジンを搭載したモデルが誕生した。このツインエアエンジンはすでに当Webサイトでも既報していが、デビューは一年前の2010年3月のジュネーブショーだ。
フィアット500に搭載されてお披露目されたツインエアは、当初、国内には2010年秋に導入という噂もあったが、実際は2011年3月末からの導入であり、待ち焦がれた人もいたことだろう。
ツインエアエンジン搭載したフィアット500は85ps、14.8kgmの出力、10・15モード燃費が21.8km/L、CO2排出が107g/kmという優れた燃費を達成している。従来の1.4Lエンジン車と比べ燃費は58%も向上しているのだ。
さて、このエンジンの何がすごいのだろうか。875CCの直噴ターボ/スタート&ストップというユニットでありダウンサイジングコンセプトのもと開発されたものだ。これまでフィアット500は1.2Lと1.4Lエンジンがラインアップされており、それが875CCとなるダウンサイジングというだけで終了したくない。
そこには見逃せないテクノロジーが結集しており、FPTをはじめとするフィアットの底力を垣間見ることができるので、当Webサイトを参照してほしい。
今回はこのツインエアを搭載したフィアット500に試乗することができたので、モータージャーナリストの津々見友彦さんのコメントとともに、その様子を届けたい。
ツインエア・エンジンは、低速域でのトルクの立ち上がりがとてもいい。875ccなのに1.4Lなみの出力というだけあって、トルクフルに感じる。実際、最大トルクは1900回転で発生する。小型のタービンが低回転から過給をはじめており、ターボ車のネガな部分であるターボラグを感じることなく高回転へとつながる。
↑吸気側にカムシャフトがなく、油圧によってバルブの開閉を行う
そして、さすがイタリア車であると感じたのは、そのエンジン音である。国産の軽自動車が660ccであり、その排気量の差からして、エンジン音に期待はしていないのだが、フィアット社はそのエンジン音の演出に力を注いで開発しているのだ。だから、2気筒であることを強く感じさせる音をつくり、そして聞こえてくる音が楽しかったり、愛嬌があったり、気持ちよかったりという、フィールが得られるようにしているのだ。
↑津々見友彦氏
「この音はなんともレトロチックなサウンドで、昔を思い出す。でも、そこは最新のテクノロジーというのだから驚きです」とはベテラン、ジャナーリストの津々見氏。
このエンジン音が実にルックスとマッチしていると感じるわけで、クルマの魅力や価値を大きく引き上げていることは間違いないだろう。もちろん、ハイテクノロジーな部分をその音からは感じることはないが、クルマ造りのうまさには感心させられてしまう。
組み合わされるミッションにも特徴があって、欧州では数多く採用されているAMTである。フィアットはツインクラッチのTCTもラインアップしているが、コンパクトカーには軽量・シンプルなAMTを採用するという戦略なのだ。日本車ではトラックなどに採用されているが、今では乗用車には存在していない。これはマニュアル構造のミッションを自動変速させる仕組みにしたもので、運転者は2ペダルでの操作になる。つまり通常のATと同じ操作方法でいい。
しかし、シフトアップ時には自動でクラッチが切れて、ギヤが1速高いギヤにシフトされ、それから再びクラッチがつながるという動作はマニュアル操作と同じであり、その変速速度はミッション任せになり、クラッチが切れた瞬間、失速する。これはマニュアルミッションの宿命とでも言えることで、どんな素早いシフトアップをしたとしても、動力が途切れる瞬間が存在する。このAMTもその瞬間が確実にあり、「運転者としてはシフトアップをするときに、アクセルを踏んだままではなく、少し抜いてあげるという操作を入れてあげたほうが、その失速感を感じないで済む」と津々見氏からのアドバイスもあった。
自らの意思でアクセルを抜いてシフトアップさせるのと、踏みっぱなしでシフトアップするのを待つのとでは、その感じ方に違いがあるからだ。この少しアクセルを抜くという操作をすることで、運転者が操作をしているというフィーリングが残り、そこもまた、痘痕もえくぼではないが、フィアット500の魅力のひとつと感じてしまう色気を持っていた。
「ハンドリングでは直進性がしっかりとあり、安心感がある」と津々見氏。いかにシティコミューターとしての使用が多いとはいえ、高速の平均速度が高い欧州だけに、そのあたりは抜かりなく仕上げてきている。そして街中での駐車ではそのハンドル操作は軽く、運転が苦手という人や、力のない女性でも楽にハンドルまわしができるようにアシストされている。このあたりも、さすがと感心させられてしまう。
乗り心地では意外にもリヤシートのスペースが広く、大人4名乗車が可能でその乗り心地もクラス同等だろう。運転席、助手席ではピッチングを感じることもない。ただ、「ロールはやや大きいと感じるのだが、イタリヤ車の滑らからでしなやかなサスペンションの血統だからでしょう。ロールするからといって、恐怖を感じることなど一切なく、逆に操作フィーリングを実感しやすいという表現のほうがいいかもしれない」とは津々見氏。
ブレーキも十分に効き、タッチも自然だ。踏力にたいしてリニアにブレーキがかかり、国産車によく見られる少しの力でしか踏んでいないのに、ブレーキがすごく効くといったことはなかった。
インテリアの印象もかわいい、おしゃれ、なのだ。ボディカラーと同色に塗られたインパネまわりも、一般的な樹脂素材であるにもかかわらず、あえて金属のパネルを想像させるように作られていて、ここにもレトロ感とモダンが共存している。国産車の多くのエントリーモデルの場合、樹脂製のインパネに遭遇すると「もうすこし、質感や見た目をよくする工夫ってできなかったのだろうか」という会話をジャーナリストたちがしているのを、試乗会場でよく耳にする。まさにお手本的存在といえるのではないだろうか。
こうして試乗を終えると、たとえ部品が安価なものでも、また、ありきたりのパーツであっても工夫次第で個性的なクルマに仕上げることができるということを実感し、クルマ造りへの情熱や見た目=デザインへの熱いこだわり、イタリア人気質というのか、すべてがおしゃれに演出されていることに魅了されていた。
文:編集部 髙橋明
関連記事
フィアットグループが実現した圧倒的技術革新 マルチエア・エンジンを開発