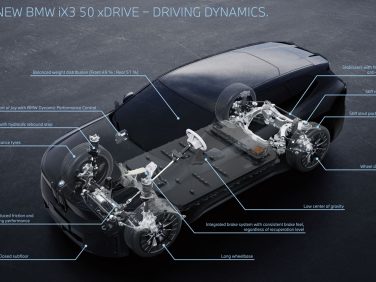国内でも徐々にその存在感が増している中国車だが、そのトップであるBYDが持つ技術のバッテリーとSDVについて詳しい情報を得る機会があったのでお伝えしよう。
グローバルでのEV普及状況(2024年データ)
まずは中国とBYDの最新事情としてNEVの現状について、BYDオートジャパンの東福寺社長から説明があった。NEVは中国政府が進める政策のひとつでNew Energy Vehicleの略。内容はPHEVとEVのことだ。中国ではこのNEVを優先したいがために、さまざまな優遇措置をNEVに行なっており、年々台数を増やしている現状がある。中国国内では50%以上がNEVへと変化しているという。
グローバルで見ると2024年のデータとして、EV普及率ではノルウェーが92%と突出して高いシェアを持っているが、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダなども50%前後の普及率になっている。ちなにみにドイツは19%と低い。欧州以外で見ると当然中国がトップで48%、続いてイスラエル、カナダと続くが20%前後というシェアで、日本は2.8%にすぎない。
また自動車のマーケットで見ると、世界に1億台のニーズがあり、2024年、中国は3148万台を占める巨大市場であることがわかる。その中国でもっとも台数を販売しているメーカーがBYDで、2025年の1〜6月期は212万台を販売。つづいて吉利汽車が1〜5月期で117万台となっている。国営企業や地方政府企業系もある中でもBYDの勢いが圧倒的であることがわかる。

余談になるが、BYDの超高級ブランドの仰望(ヤンワン)は、3500万円以上の価格帯のモデルがラインアップしているが、これが毎月200台程度が販売されている実態があるのには驚かされる。国内では中国経済の低迷や自動車産業の淘汰などのニュースがある中、実態は、かなりの富裕層が超高級車を手に入れていることがわかる。
BYDの最新“超技術”搭載モデル
さて、バッテリーの供給企業という点では、CATLが世界NO1の供給量であり、欧州のカーメーカーの多くに供給している。例えば、メルセデス・ベンツやBMW、フォルクスワーゲン、そしてテスラ、中国のZEEKRなどだ。またBYDもバッテリーサプライヤーとして、テスラ、トヨタ、スズキに供給しており、2024年のデータで17.2%のシェアを持っている。ちなみにCATLは37.9%のシェアを占めている。

さて、その躍進を続けるBYDだが、新技術も続々と開発し市場投入も行なっている。まずは「天神之眼」と「油電同速」がある。これについては下記に詳しく記載しているので参考にして欲しい。
関連記事:【驚愕】BYD ガソリン給油と同等時間で充電可能な新技術満載モデル2車種を発表
簡単にかいつまんで説明すると、「天神之眼」は自動運転を視野に入れた技術で、BYD車には全車搭載していく。LiDARやレーダーなどの機器のレベルによって3段階用意して対応。そして油電同速とはガソリンを給油する時間と同じ時間で急速充電ができるという意味で、1000Vの超高電圧アーキテクチャーを開発し、すでに実装した車両も発売しているというものだ。

これはすでに「漢L(ハン)」と「唐L(タン)」というモデルに搭載し販売されている。それらにはSuper e Platformが採用され、4大コア技術とBYDでは呼んでいる技術を搭載・対応している。つまり、超高速充電対応バッテリー、超高電圧アーキテクチャー、580kWモーター採用、そしてメガワットフラッシュ充電パイルの4つだ。
580kWモーターは30,000rpmを実現し300km/h超のスペックがある。また充電パイルは1000V/1000Aというこれまで800Vがメインだったが、さらに高電圧の急速充電が可能になっている。それに伴うサーマルマネージメントも新規に開発し、上下にヒートエクスチェンジャーを配置した3次元立体流路を持つシステムで温度管理を行ない、-20度Cから60度Cまで安定的な充電ができるとしている。それらに伴うSiCも自社開発していることで、超高電圧で超高速充電が可能になっているのだ。

日本市場投入予定の軽規格EVハイトワゴン

そしてPHEVが新技術として登場し、第5世代になるPHEVは熱効率46%のICEを搭載し、航続距離は2000kmに及ぶモデルを開発している。PHEVとはいえ、内容はレンジエクステンダーで、水平対向エンジンを発電機として開発し搭載している。
関連記事:BYD 世界の頂点を狙うプレミアムブランド「ヤンワン」と水平対向4気筒ターボエンジンのPHEV
そして注目なのは日本市場に軽自動車規格のEVを投入することだ。こちらは2026年後半に予定しており、現在開発の最終段階にあるという。ベンチマークはホンダ・NーBOXで、ハイトワゴンでスライドドアを装備したEVだ。車両の大きさは日本の軽規格で製造されるという。
また、バッテリーの保証は従来8年15万kmとしているが、2万円を支払うと10年30万kmの延長保証ができるプランも用意し、安心してEVに乗れるようなアイディアも投入している。さらに認定中古車のバッテリー保証も行なっているのだ。
NMC系 vs LFP系バッテリーの発火リスクの違い
さて、多くの人の関心事にバッテリー火災があると思う。モバイルバッテリーなどリチウムイオンバッテリーは発火事故が多くあり、車両についても不安の声はある。この点に関し、BYDオートジャパン技術部門のシニアアドバイザーの三上龍哉氏は詳細に説明を行なっている。
まず現在車載のリチウムイオンバッテリーには2タイプがあり、ひとつはNMCの三元系でニッケル、マンガン、コバルトを使ったタイプ。もうひとつがLFPと言われるリン酸鉄のバッテリーだ。BYDではこのLFPを中心に車載している。

なぜリチウムイオンバッテリーが発火するのか。燃焼には可燃物がありそこに酸素が供給され熱源があると燃焼をする。三元系は層状岩塩型という構造をしており、正極にあるイオンが充電時に負極側へ移動する。この時に衝撃などが加わると、ガス化していない酸素が、その構造体から抜け出し、バッテリーパックの中にガス化した酸素が発生して発火につながるという仕組みだ。
一方、LFPは正極のイオンが個別になっている結晶構造という形で構成され、充電時にイオンが負極へ移動した際、この結晶構造が安定しているため、内部で酸素が発生しない。そのため発火リスクが小さいと説明している。
つまり何らかの衝撃が加わった時にリスクの違いがあり、LFPはリスクが小さいとしており、BYDではLFPがブレード状のセルとしているためブレードバッテリーと呼ばれるLFPを車載している。
考えてみればガソリンのような可燃物を搭載しているほうがリスクは大きいようにも感じるし、充電時や事故時のリスクはLFPであれば最小になると考えてもいいかもしれない。
OTA対応の制御系込みSDVを実現
さて、BYDが力を入れている分野のひとつにSDVがある。こちらは、コックピット(IVI)、パワー系、運転支援(AD/ADAS)、そしてボディの4つのドメインにわけ、ECUで制御している。従来の個別ECUではこの先のOTAに対応することが難しく、集約型のECUへと進化しているのだ。

その集約型ECUとしてOTAが可能になるが、その際、国際連合 欧州経済委員会 自動車基準調和世界フォーラムWP29にある「サイバーセキュリティシステムに係る協定規則(第 155 号)」と「プログラム等改変システムに係る協定規則(第 156 号)」への適合が必須になる。
これをすでにBYDでは取得しており、POSIXに準拠したAPIの標準化まで進めているのだ。いま、欧州や日本のカーメーカーはAUTOSARへの標準化で進んでいるが、BYDはすべてが自社開発・製造できるためにAUTOSARへの取り組みではなく、自社のハードとソフトウェアの同時開発によって上記のR155とR156に適合させているのだ。

噛み砕いて説明するとOTAを行なうには、ドメインECUを制御するBYD OSがソフトウェアを走らせるには、共通言語や通訳が必要であり、それらをある基準のルールで標準化する必要がある。それがPOSIXへの準拠とAPI標準化でPortable Operating System InterfaceとApplication Programing Interfaceの略。そうすることでOSとECUが連携して稼働する。反面ハッキングなどのリスクへの対応は必須であり、それがR155とR156を取得したことで、世界に販売できるというわけだ。
結果的にBYDのOTAはIVIだけでなく、制御系まで入っているSDVが実現できているということで、そうした点からも世界最先端の技術を搭載したモデルが市販されていることが理解できる。