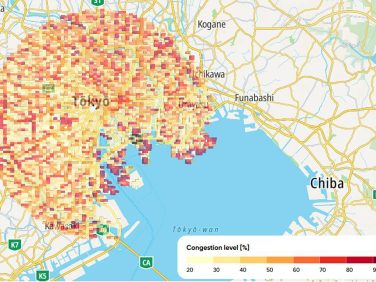ヨコハマタイヤのウインター商品であるスタッドレスタイヤに、新製品が追加された。「アイスガード8」は、好評だったアイスガード7の後継モデルで、氷上性能をさらに磨きをかけた新商品だ。その性能アップをアイスガード7と比較しながら、テストしてきたのでお伝えしよう。
テストはヨコハマタイヤのテストコースで、北海道旭川にあるT-TEC。室内テストコースもあり、充実したテスト環境を持っており、2025年2月にここを訪れ比較テストを行なった。
平均ラップタイムもアイスガード8が有利

最初のテストは室内の氷盤路の定常円旋回。アイスガード7と8の両方で旋回テストを行なった。おおよそ3分間、連続して旋回をするテストで、旋回できる限界速度、ラップタイム、そして手応えやグリップ感などのフィールチェックという項目のテストだ。
旋回を始めるために、氷上でわずかに操舵する。この時の手応えに違いがあった。切り始めのグリップ感の違いとして感じるが、大きな違いとは言えず「違いは感じられる」という程度だ。
旋回速度ではアイスガード7が約22km/h前後の速度でグリップ限界となり、滑り出す。アイスガード8では約23km/hまで速度は出せるので、グリップ力の違いは明確だった。そしてラップタイプでもアイスガード7は19秒後半が平均で、アイスガード8だと19秒前半のタイムで周回できていた。
発進時の加速力はアイスガード8が明らかに優位
アイスガード7は空転やわずかな不足あり

次に屋外に出て圧雪路のスラロームと短制動のテストだ。こちらも比較試乗ができた。しかし操舵の手応えの違いは感じるものの、グリップ力の違いまでは感じられず、あくまでも手応えのしっかり感の違いという程度だった。しかし、そのしっかり感の違いは安心感にもつながるので、製品進化は精神的にも役立っていると思う。
明確な違いとしては加速力の違いがあった。これはゼロスタートを切り、パイロンでフルブレーキをかけるのだが、アイスガード7では、パイロンまでの距離が短くテスト速度の40km/hまで、到達できないケースがあった。つまり、スタートダッシュで空転してしまい、速度があがらないということだ。一方、アイスガード8では複数回テストしたが、確実に40km/hに到達できていた。
そして次のテストでは同様にゼロスタートだが、今度は50km/hまで車速を上げる。パイロンまでの距離は延長しているが、アイスガード7ではギリギリでテスト速度に到達した。しかしアイスガード8ではパイロン手前で50km/hに到達し、速度調整ができる余裕があるグリップ力を見せたのだ。
圧雪路における発進時のグリップ力には顕著な差があったと言え、操舵応答としてはしっかり感の違いがあり、短制動では、ほぼ同等という結果だった。
多様な車種や駆動方式でも各車の走行特性を活かせる安心感がある

次に、再び室内に戻り氷上での短制動テストを行なった。氷盤路の条件は厳しく、水が少し浮いている状況で、最も滑る環境だった。室内温度は0.9度、氷盤路の温度は-1.1度。ちなみに屋外は+2.8度と気温は高い日だった。
ここでもアイスガード7と8の比較テストができ、30km/hからの急ブレーキテストだ。ABSが働くまで踏み込んで何mで停止できるかのデータを取った。
その結果、アイスガード7ではおおよそ22mで止まり、アイスガード8では20mという違いがあった。この日のテスト環境よりさらに低い温度では、ヨコハマタイヤのテストドライバーによるとアイスガード7では17、8mで止まり、アイスガード8では15、6mで止まる違いがあるという。いずれにしても、アイスガード8の氷上制動では進化がはっきりしていたのだ。
他にも圧雪路での絶対評価テストがあり、アルファードやスープラでは幅広、超扁平タイヤでもしっかりグリップすることの体感を得ている。圧雪路ではタイヤ幅が狭いほうがグリップするという都市伝説があるが、現在のスタッドレス技術では接地面積が広くてもしっかりグリップする技術を搭載している体験だった。



また、BMW1シリーズ、MINIカントリーマンALL4、テスラ・モデル3、サクラといった車型の違いや駆動方式の違いでのテストを行ない、車両の走行特性が引き出せているか?というテストも行なった。これはワインディングを模した圧雪路コースで、BMWらしさ、サクラらしさなどが損なわれていないか?というフィールテストだった。結果は言うまでもなく、安心して高いグリップ走行ができる性能を体感している。


さて、これらの氷上性能の向上、圧雪路での性能進化はどのような技術を搭載して進化したのか開発の中身を見ていこう。

まずはコンパウンドが新開発されている。高密度マイクロ吸水素材を開発し、劣化を抑制するオレンジオイルS+を新規に開発。そしてシリカの増量、マイクロエッジスティック効果を高め、より引っ掻き効果を高めている。
この高密度マイクロ吸水素材は、氷との摩擦の最大化を狙ったもので、過去最小サイズで高密度に配置することができる第8世代のコンパウンドを開発している。その結果、吸水と密着のレベルアップが実現したのだ。
ここで雪上性能と氷上性能では相反性能であることもお伝えしておこう。大きく分けて雪上、氷上性能は、圧縮抵抗、雪柱せんだん力、エッジ効果、凝着摩擦力という4つの領域で性能を開発している。
氷の路面ではエッジ効果とそして最も重要なのが凝着摩擦力になる。一方雪上では雪柱せんだん力が重要と考えられており、つまり接地面積が広いほど氷には効き、溝がないほうが効果は高い。雪上では溝面積が多い方が効果が高いわけで、雪上性能と氷上性能は、相反性能になっている。
そこで前モデルのアイスガード7(IG70)では双方に効くエッジ効果によって性能を上げてきた。そしてアイスガード8では、そのエッジ効果をさらに高いレベルでバランスさせた商品としている。新開発したコンパウンドでグリップ力が上がり、溝エッジ量を4%増加させたトレッドパターンの開発を行ない、氷上、雪上性能のレベルアップができたとしている。とりわけ、トレッド幅をのみを8%広げて接地面積を確保して氷上性能が向上している。
またトレッドパターンはトレッド幅の拡大に合わせて、リブの大型化、センター部とアウト側のブロックも大型化することでブロック剛性も6%向上させている。このブロック剛性と接地面積の拡大により氷上性能を大きく向上することに成功したのだ。
また新開発のコンパウンド性能を活かすためにもマイクログルーブの見直しも行ない、グルーブの太さや角度、密度の最適化をしたものを採用している。
また横方向の溝の数や幅、長さを変更し溝エッジ量を4%増加させている。また周方向の溝を大容量化することで、排雪、排水、旋回時のエッジ効果を高め、雪上性能の向上をさせている。
そしてラグ溝の倒れ込み抑制サイプを採用し、サイプが積極的に倒れることでラグ溝の変形を抑制することに成功し雪上性能の向上に繋げているのだ。とくにアウト側のトレッドに採用している。
これらの技術を搭載したことで、アイスガード7に対し雪上性能、氷上性能、そして長く効く性能が向上しているのがアイスガード8なのだ。