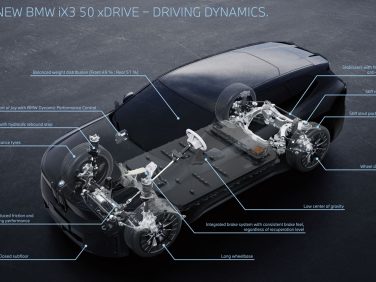国産車ビンテージ
良いワインが造れた年はビンテージと呼ばれるが、国産車のビンテージは1989年を挟む4年間だと思う。
1989年には、後に名車と呼ばれることになる初代のモデルが登場している。たとえば後にレクサスと車名が変わるが初代のセルシオだ。あるいは初代のホンダNSXもデビューしている。R32型の日産・スカイランGT-Rも復活した。そして当時はユーノスロードスターと呼ばれたマツダ・ロードスターも登場した。
ちなみにバブル景気に浮かれた私はユーノスロードスターとスカイラインGT-Rのオーナーになった。その前年の1988年にはシーマが登場した。後に「シーマ現象」と呼ばれ、高級品を次から次へと大衆が買い求める1億総上流の代名詞となった国産高級車である。今回の話はそのシーマから始まる。さらに付け加えると1991年にはホンダS660につながることになるビートが発売となる。
自動車好きにとっては、1988年から1991年はビンテージだった。そして、それらは、みんな自分で運転する自動車だった。ああ。
次世代車はつまらない
次世代車をめぐる旅は、自動車好きにはガッカリすることが多いが、避けては通れない。そんな話から始めようと思う。しかし、旅は寄り道が楽しい。だからこの旅も寄り道の旅である。
しかし、エンジン好きというか、これまでの内燃機関を使う自動車が好きな人にとっては、次世代車はなかなか受け入れがたい自動車だと思う。特に電気自動車や燃料電池車は、音もしないし、臭いもなく、振動もないし、初めからトルクが最大なのでトルクの盛り上がりもない。「こんなクルマに乗るくらいなら自動車なかやめてやる」と思ったとしてもごくまっとうである。
だからといって、内燃機関式次世代車も場合によっては噴飯ものだ。たとえば、アトキンソンサイクルだ、ミラーサイクルだといった省エネエンジンはトルクが薄くて、私は嫌いだ。それとハイブリッドを組み合わせたトヨタ式は、加速のフィーリングが悪く高級車には向かないと思う。同様にCVTとの組み合わせも少しも気持ち良くない。
最悪なのは、ひたすら空燃比を薄くしただけのエンジンの載った燃費カーだ。これとアイドリング・ストップ機構が組み合わさると、出足がひどく鈍く、アクセルを踏んでもすぐに発進せず、加速力も弱いので、交差点での右折がたまらなく怖い。アクティブセーフティという本当に大事な安全性を考えるべきだ。
電気はなかなかだ
しかし、たとえばBMWのi3は、トヨタ86よりも0-100km/h加速が速いだけあって、その加速の快感に酔いしれるBMWのMシリーズ愛好家が多いと聞く。さらにテスラのモデルSの加速はとても気持ち良く、夏には日本にも入るはずのメルセデスC350e(プラグインハイブリッド)は、Cクラスの中でもっとも速く、最高のハンドリングだと思う。

いやいや、だから内燃機関自動車愛好家は、よけいに腹が立つのでしたね。ただ、電気自動車がこれほど楽しくなったのはつい最近の話であり、プラグインハイブリッド車は始まったばかり。昔はみんな遅かったのですよ。
しかし、C350eに乗ると、これからの省エネ型内燃機関は何らかの電気的動力補助がないと、気持ち良い加速が味わえないと思う。内燃機関に電気動力が加わるとこれまで味わったことのない気持ちの良い加速感が味わえる。

C350eは、ダウンサイジングしてエンジンを軽く、コンパクトにし、さらに軸受けやピストン、ピストンリング等の物理的フリクションを低減して高効率化し、小排気量によるパワーダウンをターボ過給することで防ぎつつ、ターボ過給のアクセルレスポンスの悪さを電気モーターを働かせることで補っている。それがとてもよくまとまっていると同時に、最高の加速感を味わえるのだ。

それだけではない。街中では電気自動車になる。これがまた、たまらなくいい。静か、無臭、高レスポンス、大トルクによる良い加速感が用意されているのである。ダウンサイジング+ターボ過給+モーターアシストという組み合わせは、2020年から25年までの次世代車のベンチマークだ。
<次ページへ>

運転しない自動車
え、日本にはまだそんな「いい自動車」はないってか。そうなのです。日本の次世代車は、乗る楽しさを徹底的に無視して、ひたすら燃費という数値だけを追いかけてしまった。いや、そもそも自動車は乗って楽しい道具だという概念とか価値観がない方々の労作なのである。ご苦労なことだ。
国産燃費車に乗ると、未来の自動車に夢が抱けなくなる。しかし、ヨーロッパ車の場合は、まだ一部だが「自動車って、けっこういけるかも」と思える。いったいこの違いは何なのか。
では、自分では運転しないというか、運転できないというか、いわゆる自動運転車はどうなのだろう。そもそも自分で運転しないのだから、運転する楽しさなど、あるはずもないのかもしれない。だが、それが近々に現れる。自動運転車の登場は避けては通れず、必ずやってくる未来なのだ。
その片鱗は、先のシーマあった。私は東名高速道路の海老名SAから用賀料金所手前まで、まったくハンドルにもアクセルにも、ブレーキにも、シフトノブにも触らずに走った。
シーマといっても1991年に登場した二代目かもしれない。記憶は確かではないが、すでに半自動運転システムが装備されていた。しかも、当時の法律では運転者がハンドルから完全に手を離しても、減速せず走り続けることができた。
ちなみに、やがてハンドルから手を離すことはまかりならぬというごくまっとうなお上(国土交通省)のご指導により、現在の半自動運転システムはハンドルから手を離すと解除されてしまう。
某雑誌の恒例のトークの取材で編集スタッフと箱根に出かけた私は、復路の海老名SAでシーマに乗り替えた。SAから出ると、追走するローダーを見つけてスピードコントローラーを時速100km/hに設定した。ローダーは左車線を時速80km/hほどで走っていた。
追走を始めると、私はまずハンドルから手を離し、腕組みをした。隣りの編集スタッフが焦りはじめたのがわかった。そんなことは無視して、今度はアクセルから足を離し、シートにあぐらをかいた。編集スタッフは悲鳴を上げた。そして、頼むから自分で運転してほしいと私に懇願した。
私は、「大丈夫だ。天下の日産の優秀なエンジニアが設計したのだ。運転に失敗するわけがない。このまま用賀まで走る」といった。

のんびりと自動運転のはずが…
実際、何の問題もなかった。私は時速80km/hほどで走るローダーから20m近く離れて、のんびりと自動運転で走った。隣で震える編集スタッフを冗談で煙に巻きながら、海老名SAから用賀までの30分余りのドライブを楽しんだ。
だが、前方を走るローダーが進路を変え、視界から消えて用賀料金所が眼に入ると、事態は切迫したものになった。シーマが急加速を始めたのだ。ぐんぐんスピードを上げ、時速100㎞/hまで加速した。
私は、まず組んでいた腕をほどいてハンドルを握り、シートから足を延ばしてブレーキペダルに乗せた。すると今度はシーマは急激に左に曲がり始めた。あわてた私は、事態の急変の原因がつかめなかった。
混乱する頭にめぐったイメージは、白線をカメラで認識し、ハンドルを操作するという自動運転の仕組みだった。用賀料金所が近づくと道路を区別する白線が消える。しかも前を走っていたローダーがいなくなったので、設定した時速100km/hまで加速しながら、従うべき白線を探してシーマは急激に左旋回を始めたのだった。
私は、私は……。ああ。続きは次回に。